バトントワーリングを人生の糧に──相模女子中高コーチ吉田有希氏インタビュー
- ゼミ 横山

- 2025年1月13日
- 読了時間: 14分
更新日:2025年1月21日
宮本栞里 水野姫花 新井凜
今回インタビューさせていただいたのは、相模女子大学中学部・高等部のバトントワーリング部のコーチをされている吉田有希さんです。バトントワーリングにおいてのコーチはどんなお仕事なのか。インタビューから見えてきたのは、演出力のみならず生徒への思いと技量に合わせた工夫でした。今回は、コーチとしての指導に焦点を当ててお話を伺いました。
吉田有希さんプロフィール

バトントワーリングは小学校6年生から現在まで継続中。中学入学時からバトントワーリング日本1位であるPL学園に所属し、大阪の寮に6年間通う。チームで4回優勝、高校2年生で日本代表になり、国際大会で2位を獲得。大学は日本体育大学に所属し2年生まで毎年世界大会に出場していた。その後、卒業と共にSAMURAI ROCK ORCHESTRA(*)に入団。 プロになって11年、プロ兼指導者として今がある。
*世界レベルのアスリート、メダリストによる驚愕のパフォーマンスに生演奏・プロジェクションマッピングを融合したセリフのない新感覚アクロバットミュージカル(SAMURAIROCK ORCHESTRA公式ホームページ)
コーチとしての仕事
──作品はどのような過程で作り上げているのでしょうか?
吉田:審査員は上から演技を見るので、フォーメーションにおいて円が四角になる、円から縦に並ぶ、など見せたいものを明確にしないと伝わりません。なので、とにかくずっと曲を聴いて振り付けや動きのインスピレーションを受けています。そのなかで先に見せたいフォーメーションの形を思いついたり、踊りを思いついたり、動きから動きを考えたり、動きのためにフォーメーションを考えたり、様々ですね。
ただ、自分の感覚だけでやっていても伝わらないときは伝わらないので、できる限り分かりやすくしたいなとは思っています。特に中学生の演技は複雑にしたところで本人たちにも理解できない。そして結局見せたいものが見せられないと思うんです。例えば、作品内で全員で円を作る感覚も技術もまだ身についていない子がいたり、本人たちの足の速さが関係することもあります。やりたいこととできることはやはり違うので、色々と悩みます。
──振り付け、フォーメーションなど多岐に渡る仕事を遂行するには、どのような能力、技術、知識が必要でしょうか?
吉田:知識に関しては、踊る子たちの技術レベルをまずは理解していないといけないんだよね。それは身体能力的な部分だったり、3分や3分半踊り続ける体力を考えて、生徒たちのできることを理解した上で作らないといけない。自分ができることで考えてしまうと、生徒たちが実際にやってみたときに全くできずに、じゃあ変えようかとなる。そうなると限られた時間のなかでロスになってしまうんです。だから、このくらいまでなら大会までにはできるようになるだろう、というボーダーラインを見極めるところが難しい。ギリギリを攻めないと大会で他のチームに勝つのは難しいと思うし。
でも結局フォーメーションなんかはインスピレーションで、基本的には「降りてくるの待ち」みたいな感じです。ずっと音楽を聴いていて、ここでこういう動きをしたらいいなとか。ただし自分のインスピレーションだけだと偏るから、外からの知識もちゃんと入れます。例えばバトン大会のDVDを見てフォーメーションの動かし方の勉強はしているし、バトンだけではなくて、分母が大きくて最先端の表現があるダンスの大会のフォーメーションを見たり。そういった外からの知識は大事で、舞台や全く関係のない競技からでも得るものはあると思います。多様な分野を見ていった方が、一本調子にならないかなとは思っています。
──バトンの大会においては、どのような部分が評価されるのでしょうか。揃い方であったり、バトンを扱う技術そのものであったり、比重についてどのような印象をお持ちですか。
吉田:学校団体はどちらかというと集団美。一般団体だともう少しアーティスティックなものを求められるのですが、学校団体だと、とにかく揃っていて個性を出しすぎない、という方が分かりやすくもある。難しいことをして揃わないなら、簡単でも揃った方がいい。みんなで何かをする、みんなで一つの作品を作り上げるということが、学校団体には求められてると思います。ですから、バトンの技重視ではなく、隊形を綺麗に揃えて、一つの作品としてトータルで仕上げることを目標にやっているかな。
特に中学生は揃えるのがすごく難しい。バトンを回したことがない子が、突然回して揃えることを求められるから。それをずっと練習していると思います。
技能継承
──技術を教えるにあたって、よく出る言葉や伝え方はありますか?
効果音が多いです。「ドン」とか、手を「バン」って出してとか、結局自分の感覚にはなっちゃいますけどね。あとは細かく噛み砕いて伝えています。息する息しないは結構大切で、「吐いたら力が抜けるね」「空気を吐きながらこういう動きをしようね」みたいに伝えます。初めて習うときって多分何も覚えられないんですよ。だから特に中学生は、インスピレーションは後にして、まずは形を教える。
動きはカチカチでもいいから、形を整えてから、そこにプラスでニュアンスを作っていく。分割して、ですね。慣れてる人はいいんですけど、慣れてない人は、同時にやっちゃうと無理なんです。形ができればとりあえず揃える練習はできるので、慣れてきて動きが体に入ったら、「手だけじゃなくて上半身も使って」「もっと遠くに」みたいに分割して教えます。そうすることで体に入るようにしています。

──今までバトンをやってきたからこそ、今の教え方になっているのですか?それとも講師としての経験、感覚ですか?
吉田:感覚によってですね、結局先生によって違います。僕の場合は、バトンの種目として技術を習った先生はいたんですけど、実際にバトンの教え方を習う先生はいませんでした。そして、普通はバトンの教え方がどのようなものなのかを習う研修期間のようなものがあるんですけど、相模女子を任された当時はありませんでした。なので、めっちゃ試行錯誤だったんだよね(笑)。
そういうわけで僕は、相模女子に合ったやり方を探しました。学校によっては経験者が入れますという場所や、初心者しか入れませんという場所があるなかで、相模女子は中高一貫で経験者も初心者もいるという特殊な学校だったので、そういう意味でも少し大変でした。
人によって「なんとなく部活に入る」「バトンをしに部活に入る」など、部活に対するやり方は違うと思う。僕の母校は「バトンをしに部活に入る」方だった。だから、演技も教え方も自分が選手だったときのことはあまり参考にならないんだよ(笑)。自分の感覚でやるしかありませんでした。でも、生徒の部活に対しての熱意にばらつきがあっても、それでムカついたりはしないです。元々バトンを経験してて、部活に入りたい気持ちがあった子たちはそれは熱意はあるし、真面目にやる。でもそうじゃない子たちってやっぱり遊びたい気持ちもあるしサボる子もいるわけです。感覚が違うのは当たり前だから、全然理解はできるんですよ。一番遊びたい盛りで毎日練習させてね。こんなはずじゃなかったって思ったことあるでしょ。
──はい(笑)。
吉田:だよね(笑)。でもやるときはやる子たちでもある。だからやっぱりその子たちに合った指導で押していかなきゃと思っていました。最初は距離感がわからなかったから、めっちゃ優しくしてね(笑)。それでも途中で「いけるな」と思ったらスイッチを入れて、2、3年生で指導をきつくしていくわけです。
でも、本当に女子校は難しい。僕は共学だったから、女子高の空気感は本当に分からず、最初は猫被ってました。でも僕は結構ね、生徒と楽な関係を築くことが多いから、みんなも楽にやってくれてて助かっていました。でもやっぱり今の時代、先生と生徒の関係は結構難しいから、指導は試行錯誤ですね。今は特に言葉使いとか、それから細かいポーズの指導で、例えば腕をもっと上げるんだよと伝えるためにどうしても触らなければならないときなんかは、「ちょっと触るよ」って言ったりするように気をつけています。
あとは関係をきちんと作ることも心がけています。長年付き合ってる生徒は僕がどういう人か分かってる。でも入ってきたばかりの中学生に、最初からその感覚で行くとダメなんだよね。接し方に気をつけないと何が起きるか分からないからね。そういう面でも、世間話とかをしてちゃんと人と人との関係を作っていかないと良い作品もできないと思ってます。
下克上の秘訣
──相模女子は最初、私が入学当時は関東大会ワースト2位とかそのくらいだったと思います。でも、中学3年生でいきなり関東1位とって、高校でも金賞を取ったり、その原因はどこにあると思いますか?
吉田:僕が一番最初に相模女子を見るってなったときにやらなきゃいけないなって思ったことがあります。例えば今、相模女子の中学は、演技の中で全員で1スピン(バトンを投げて一回転して取るという技)を行うんですよ。それが当たり前にできる基準なんですよ。でも、僕が来た当時は、その当たり前がトス(バトンを投げて回らずに取る技)でした。つまり、1スピンはすごい技で、3年生とか、できる人がするという認識があったんです。
なので、このチームを勝たせなきゃいけないってなったときに、「1スピンなんて難しい技」という固定概念を崩して、一新させなければならないと思いました。そういうのって、意外とやってみたらできるんだよね。運動神経の良い子は特に、固定概念さえなければすぐできちゃう。例えば自分が入部したときに、三年生がじゃあちょっとチャレンジしてみようよのレベルだとできないと思ってしまうけど、みんなが当たり前にできていれば、なんとしてでもやろうとして、できちゃう。
そんなように一つ上のレベルを提示してあげれば、意外と気持ちの問題でどうにかできてしまうんだよね。だから、あなたたちの代は1スピンが当たり前だったよね。だから3年計画で、あなたたちの代が3年生になって全員の基準が揃ったときに一番良い賞が取れるよう考えていました。
あと、あなたたちの代には経験者がいたから、もっと上を狙えそうだなという気持ちで、特に多分厳しくしたよね(笑)。厳しかったっていうか、なんて言うんだろう。求めるものが大きかったし、やってみる気持ちも高くて勝手に色々練習してくれてたから。だから、固定概念を崩すっていう努力が僕の中で一番かな。
──その感覚、すごくわかります。私も体操やっていて、やっている人が一人しかいない技とか経験者の先輩がやってる技だと「ちょっと卒業までにできないかな」みたいに最初は思うんですけど、先生に「やってみればいいじゃん」って言われるとちょっとできそうかもと思って、そうするとやりたくなるみたいなところがありました。
吉田:そうそう、そんな感じ。体操で言うと例えば、初心者は「バク転までしかやりません」より、「宙返りまでやります」っていう方がいい。そこのレベルに達するまで練習してできるようになるんだよね。だから相模女子も、最初は大変だろうなと思ってたけど、何年かけてでも「難しい技」を「当たり前の技」にしていかないといけなかった。そうしないと、付け焼き刃で「難しい技」が上手くいくときもあるかもしれないけど、連続で勝つのは絶対に無理だと思います。
バトンは体操とかと比べると怪我をするリスクは小さいから、「とにかくやって落とせばいいじゃん、失敗すればいいじゃん。別に失敗が悪いと思わないから」という気持ちでした。あとはまあ、関東1位が取れたのは本番の演技が良かったからだよね。ノードロップだったし。やっぱりバトンは床にバトンを落としたりするミスがすごく目立つから、運の要素もあります。
──今は何をモチベーションとして仕事をされてますか?
吉田:好きだからやってます、基本的には。趣味がバトンだから。良い作品が作れて、それが周りに喜んでもらえたりとか褒めてもらえたりっていうのはやっぱりモチベーションにつながるね。あとは自分が考えたものが形になるっていうのがやっぱ楽しい。好きなものを仕事にしちゃったから、その辺で良くも悪くもなんだけどね。ずっとバトンのことしか考えてないです。
コーチとしての未来
──団体と個人の目標を教えて頂きたいです。
吉田:団体の目標は、関東1位を安定して取って「関東と言えば相模女子」と言われるような存在にしていきたいです。去年、高校生は初めての関東1位。中学生は何年か連続で取らせてもらっているけど、まだ安定しているわけではないですね。そして、今は関西や九州の方がレベルが高いので、全国で上の方に立ちたいです。個人でやってる子たちの目標は、全国上位にして日本代表にしてあげたいという思いがあります。
勝負の世界だから絶対とは言えないけど、すごく可能性のある子たちがいるから、日本代表になれるくらいの選手を育てることができたら嬉しいです。僕は大きな目標よりも少しずつ設定を上げていくタイプだから、生徒たちのレベルに合った目標を立てて、少しずつクリアしていこうと思っています。
教えている側として、生徒が何かできたときは嬉しいです。やっぱり気持ちの繋がりがあるから、できたら本人と同じだけ嬉しいし、その子たちがいい成績を取れれば嬉しい。「本番で成功しました」とか「本番で良い成績取れました」とか、やっぱりそういう嬉しそうな声を聞くためにやっているね。
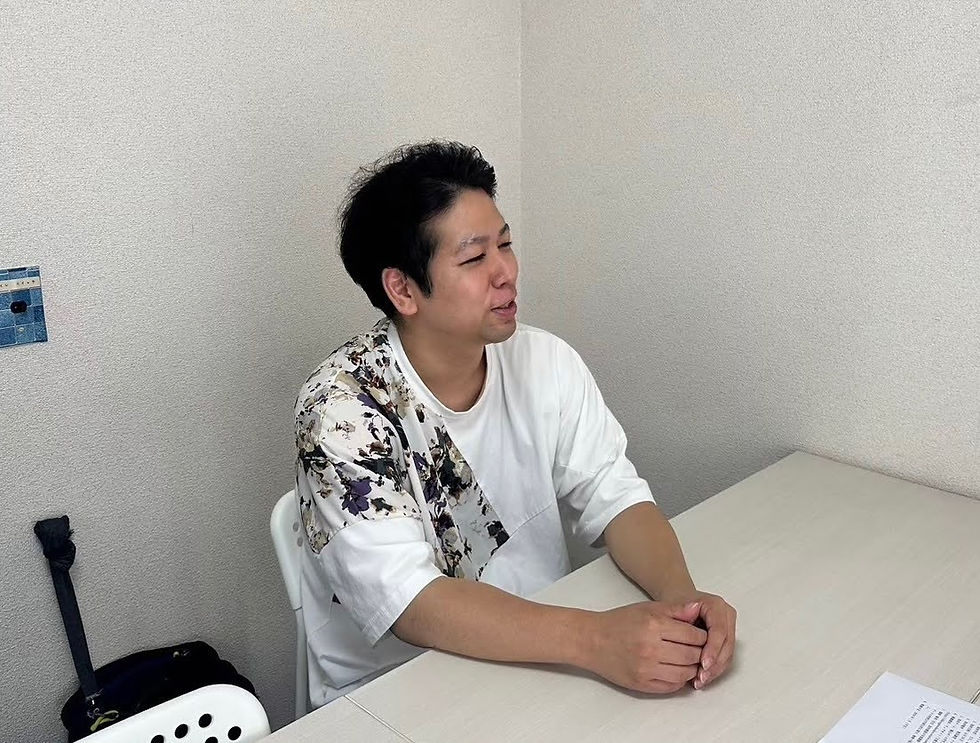
──パラリンピックのオープニングでバトントワーリングが披露されるなど、徐々に認知度は高まってきていると思うのですが、今後、バトンの未来はどう変化していってほしいですか?
吉田:もちろんオリンピックとか大きな目標はあると思うけど、バトンはまだマイナー競技だと思うので、まずはもっと認知されてほしいです。SNSとか地方新聞に載せてもらうとか、本人たちが頑張ったものを形として残すという細かいところから始めたいです。相模女子も良い成績を取ってるけど、メジャー競技で全国大会に行くのとは、周りへの伝わり方が違うもんね。せっかく生徒が学生生活の青春をすべてかけて練習しているわけだから、そのぶん先生や親御さんには「すごいね」って言ってもらいたい。頑張ったときに何が嬉しいかって、やっぱ褒めてもらうことが一番で、だからこそ僕は、色んな人に知ってもらえることが今教えてる生徒のためになるんじゃないかなって思っています。
──競技を見たことがない人には、何がすごいかわからない、みたいな部分がありますよね。
吉田:そうそう。バトンも「回ってるからすごい!」みたいな漠然とした印象しかなくて。だからやっぱり認知されることってすごく大事だよね。
教え子への想い
──今まで教えてきた生徒たちに何か伝えたいことはありますか?
吉田:6年間、あるいは3年間、本当だったら遊べたんだよね。みんな、本当は遊びたかったと思う。全ての学生生活をバトン部に捧げてもったいないなって思ったかもしれない。でも絶対にこの先のことにプラスになるはずです。逆に、それをやらなかったことの方が僕はもったいないと思ってる。
中高6年間で部活っていうのはそのときしかできないことだし、何かを長く続けるのって人間関係も含めて本当に難しいことだと思う。遊びたいとか、受験とか、色々な要因で続けられないこともあるなかで、6年続けたっていうのはすごいことで、なかなかできないことです。だから、なんて言うんだろう、自信を持ってほしいかな。何かに失敗したりつまずいたときに、「でも私はこれだけ頑張ってきた経験があるから」っていうのを人生の糧にしてくれたら嬉しいな。
努力できるって、すごい才能なんだよね。努力できる才能、続ける才能って、まあみんなにあるわけじゃないから、この先の人生で何歳になろうがどこに行こうが、自分のプライドとか自信にしてほしい。そういう気持ちでこの先も生きてほしい。全国大会に出るのもなかなか経験できることじゃないから、それも誇りに思ってほしい。僕にとってもそんな生徒が誇りです。だから、何かあったらバトン部時代を思い出して、頑張ってください。
──ありがとうございました。
編集後記
宮本:私自身、中高6年間バトントワーリング部に所属し吉田さんの指導を受けていたため、今回のインタビューは過去を振り返りながら楽しく行うことができました。特に、当時は「他のチームと違うな、吉田さんの演出は何かがすごい」という漠然とした感想だけであったため、演出面についてのお話は非常に新鮮でした。取材により分かったフォーメーションの考え方・生徒の技量・熱量等の柔軟な視野の広げ方は、改めて吉田さんにしかできないことだなと感じました。相模女子のバトントワーリング部は日々成長しており、私はもう「関東と言えば相模女子!」と感じています。今後も応援していきたいです。貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
水野:「固定概念を崩す」というお話が印象的でした。難しくてできるわけのない技から、みんな当たり前にできるようにする技に印象が変わることで、その考え方一つだけでもチーム全体の技術の底上げに大きく影響するという点が面白く、チームであったり、部活動だからこそ生まれる環境の作り方があるなと感じました。指導法や生徒との距離感などはじめは試行錯誤されたということでしたが、モチベーションのばらつきがある集団のなかで、それぞれに小さな目標を与え、それを積み重ねることで結果に繋がっているのではないかと、お話を通して感じました。
新井:このインタビューを通して、吉田さんの情熱と指導哲学が深く伝わってきました。吉田さんは、生徒たちの技術と個性を見極めながら、集団としての完成度を追求し、試行錯誤を重ねて作品を作り上げていることがわかりました。また、生徒たちにとって挑戦や努力がもたらす成長を重視し、それが将来の自信と誇りにつながると信じていらっしゃいます。バトンを「ただの技術」ではなく、「人生の糧」として教える姿勢からは、指導者としての深い愛情と信念が感じられました。



コメント